 072-803-8019
072-803-8019 
土日祝も対応いたします

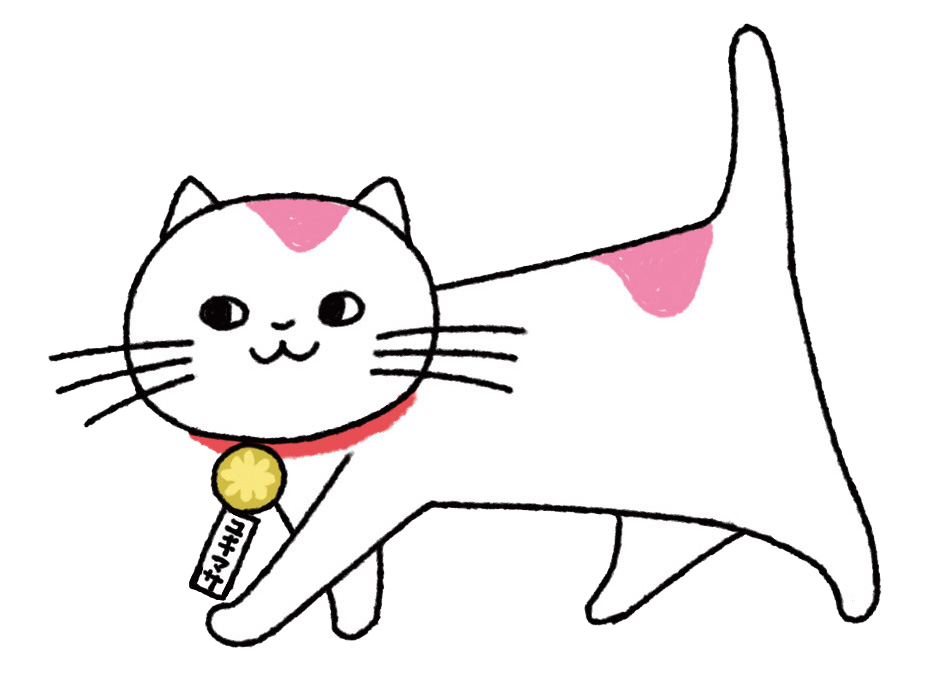

| ・引き続き5年以上日本に住所を有すること。 |
|---|
| ・20歳以上で、かつ、自分の国の法律によって能力を有すること。(つまり、自分の国の法律上、成年に達していること。) ただし、未成年者の場合は、親が帰化許可申請を出せば「日本国民の子」ということで、この条件は問題にならなくなります。実際、親と未成年の子供が同時に帰化許可申請をすることが可能です。 |
| ・素行が善良であること。これは前科や非行歴、納税義務を果たしているかどうかによって判断されるものと考えられます。 |
| ・自分、もしくは生計をひとつにする配偶者、その他の親族の資産・技能によって生計を営むことができること。 |
| ・無国籍、もしくは日本の国籍の取得によってそれまでの国籍を失うこと。 |
| ・政府を暴力で破壊することを企てたり、不法団体を結成・加入したりしないこと。 |

| ・在留年数が基準を満たすか(継続した在留年数が10年以上で、現在取得している資格が最長であるか) |
|---|
| ・生計維持能力が充分か(日本で生活する上で支障をきたさない額が確保可能か) |
| ・素行が善良か(日本法に対する遵法精神) |
| ・身分に基づく資格からの変更なら、身分証明可能かどうか(申請人の方が日本人の配偶者である場合 配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書)) |
| 手数料として8,000円必要(印紙で納付) |
| ※これらは最低の条件です。 |

| ①在留資格認定証明書交付申請(招聘手続)/th> |
|---|
| ②在留期間更新許可申請 |
| ③在留資格変更許可申請 |
| ④永住許可申請 |
| ⑤再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等) |
| ⑥資格外活動許可申請(学生アルバイト等) |
| ⑦就労資格証明書交付申請(転職等) |



